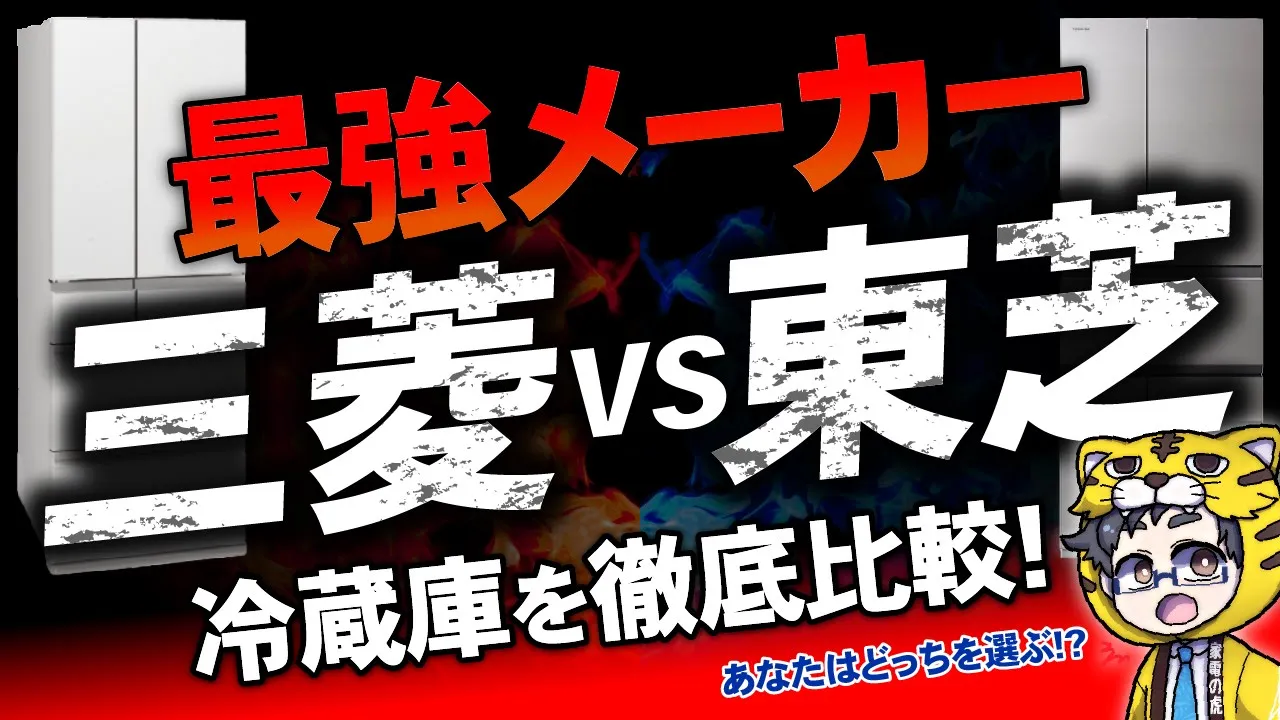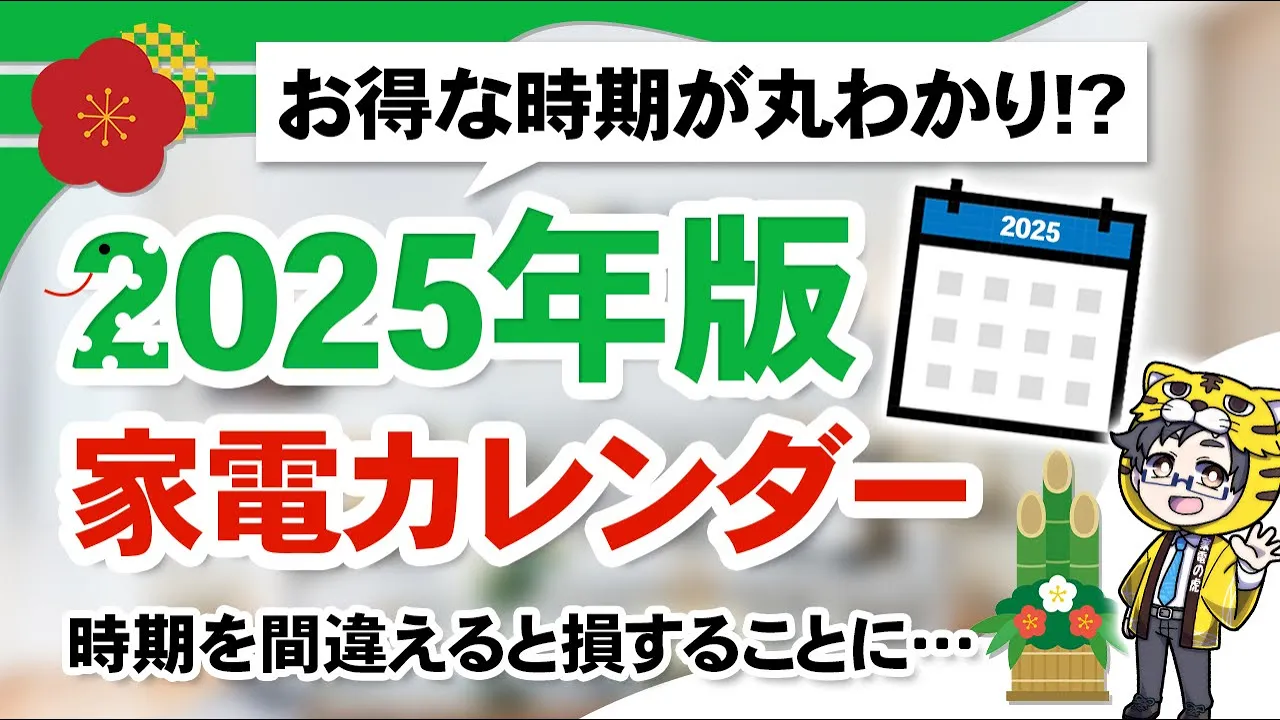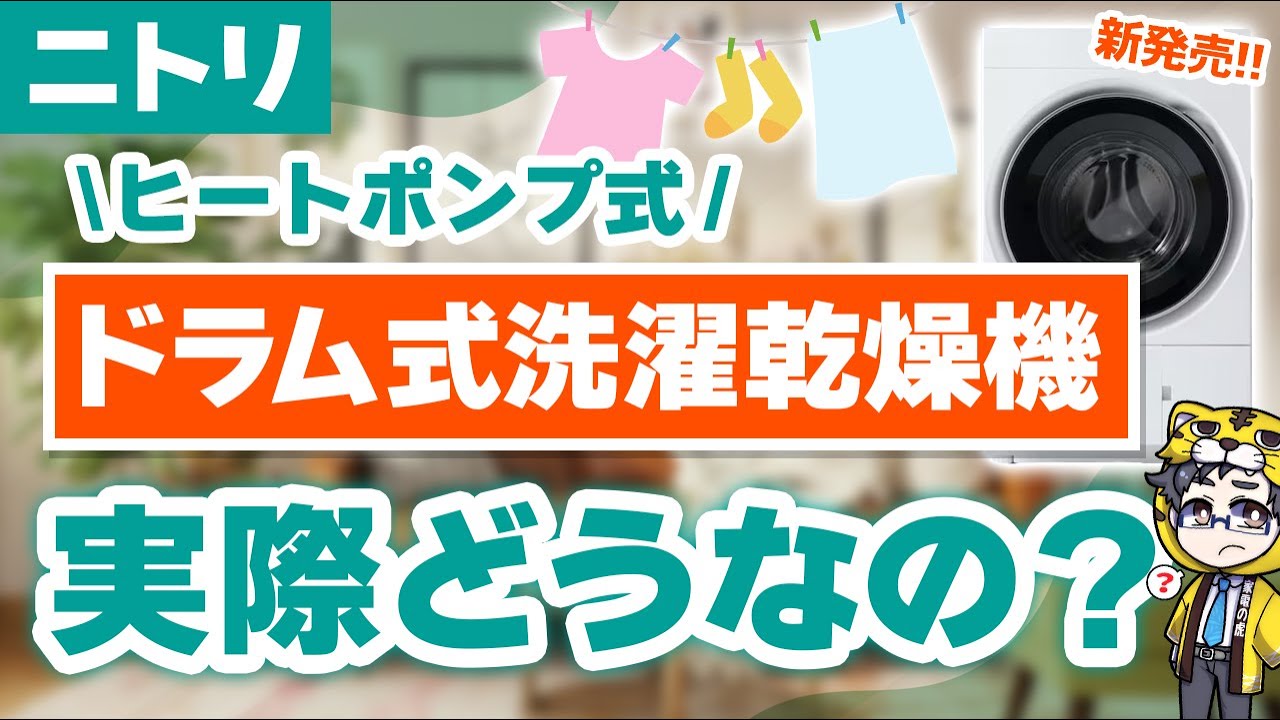いらっしゃいませ、家電の虎です。
梅雨になる前に買うべき家電、それは除湿機になります。毎年なんですが梅雨になると売り切れて諦める方や欲しい商品がなく妥協して別の商品にするって方を見ています。
そもそも価格コムで売れている商品がすべての家庭に合うというわけではありません。
そこで今回は皆さんに最適な除湿機選びをご紹介し、おすすめのモデルをいくつか発表していきます。
最適な除湿機の選び方とは?
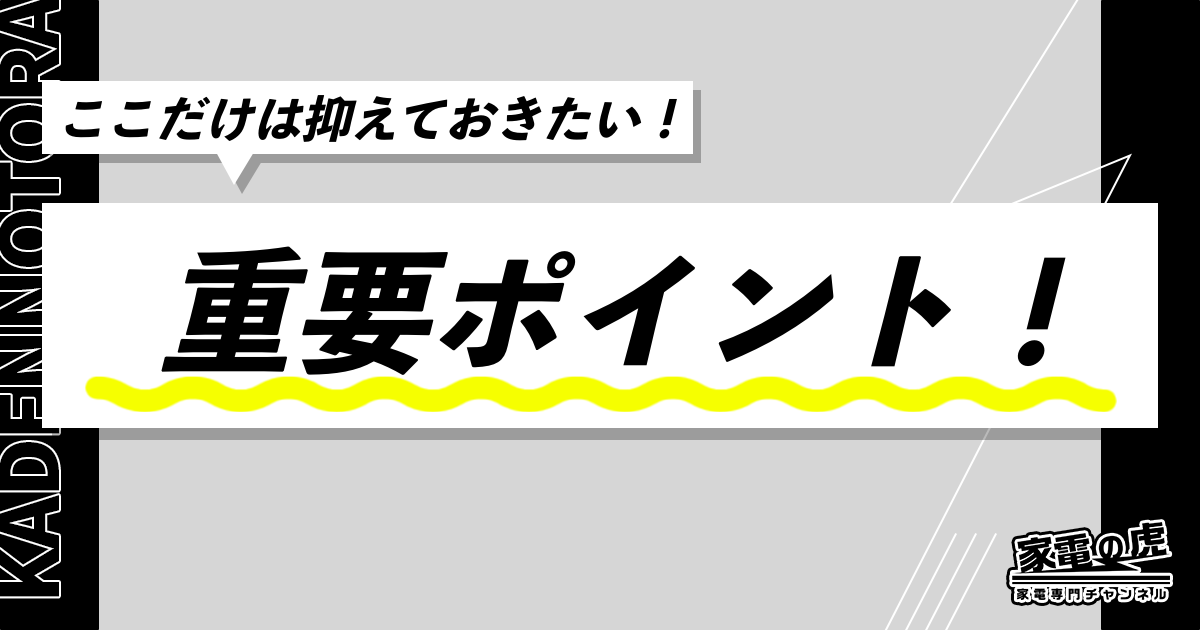
除湿機には3種類あります。
そして除湿方式は2種類あります。
除湿方式の2種類とは【デシカント方式】と【コンプレッサー方式】という除湿方式があります。
そして、除湿の3種類とは、【デシカント式除湿機】、【コンプレッサー式除湿機】、そして【ハイブリッド式除湿機】の3種類となっています。
それぞれの特徴を解説していきます。
デシカント式除湿機の特徴
デシカント式除湿機の特徴は
1,運転音が静か
2,寒い場所でも除湿能力が落ちない
3,本体が小型で軽量
この3つが挙げられます。
順番に解説していきます。
特徴①:運転音が静か
機種にもよりますが、デシカント式の除湿機の運転音は、40~50dBの間くらいです。
この後解説するコンプレッサー式の除湿機の運転音は、除湿容量によっては音の大きい機種もあります。
また、本体の動作時に振動も少なく集合住宅に住んでいる方でも、近隣に住まれている方の影響を心配する必要もありません。
「深夜に洗濯物を干して一晩中除湿機を使いたいけど、除湿機の運転の音が気になって使えない…」
という方の声をよく耳にします。
デシカント式除湿機は送風運転を強モードなどで運転すると大きな音が出るときもありますが、モーターが動いて振動すると言ったこともないので、とても静かです。
【特徴②:寒い場所でも除湿能力が落ちない】
除湿機は気温によって除湿能力が変わります。
デシカント式除湿機は本体にヒーターが内蔵しているので、気温による影響を受けません。
冬の寒い部屋の中でも除湿能力が落ちることがなく、ヒーターによって空気を温めるので気温の影響を受けにくく、一年を通じて使用することができます。
特徴③:本体が小型で軽量
続いて本体の重量についてです。
コンプレッサー式の除湿機は、その名の通りコンプレッサーを内蔵しているので、本体は大きくて重たくなります。
機種によって変わりますが、デシカント式の本体の重量はおおよそ6キロ前後です。
コンプレッサー式除湿機は15〜20キロ程度と、結構重量が違います。
デシカント式除湿機は比較的コンパクトで持ち運びできる重さとサイズのものが多いです。
反対にデメリットとして
・電気代が高い
・温風が排出される
・除湿できる範囲が狭い
これらの特徴があります。
この点も解説します。
デメリット①:電気代が高い
先程も触れましたが、デシカント式除湿機はヒーターを使用するので、電気代が高めです。
消費電力は300Wくらいから、高い機種だと600Wほどの機種もあります。
機種にもよりますが、300Wの機種を使用した場合の電気代は、1時間あたり9.3円程度の電気代がかかります。
これを1日あたり12時間使用した場合、1日で112円ほど電気代がかかる計算になります。
電気ストーブやオーブンレンジ、ドライヤーと言ったヒーターを使用する家電にも同じことが言えますが、発熱させる家電にはどうしても電気代がかかってしまいます。
デメリット②:温風が排出される
ヒーターで加熱した空気をそのまま放出するので、吹き出し口から出る風は温風で、室温から5℃前後高い温度の温風が出ます。
湿度が高い季節といえば夏だと答える方が多いと思います。
気温が35℃あるのに、そこから室温が5℃くらい上がるの…?と考えたら、ちょっと手を出しづらく感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。
デメリット③:除湿範囲が狭い
本体に内蔵している乾燥剤に空気中の水分を付着させて、乾燥した空気と水分に分けるというのがデシカント式除湿機です。
乾燥剤の大きさに制限があるので、一度に乾燥できる水分量に限りがあります。
そのため、短時間で空気中の水分を除去できる効率がコンプレッサー式除湿機のほうが高いということになります。
コンプレッサー式除湿機の特徴
コンプレッサー式除湿機の特徴は
1,電気代が安い
2,室温があまり上がらない
3,広い空間に適している
この3点が特徴です。
こちらも解説していきます。
特徴①:電気代が安い
デシカント式除湿機は空気をヒーターで温めますが、コンプレッサー式除湿機はヒーターを使用せず、取り込んだ空気を冷却します。
これはドラム式洗濯機のヒートポンプ乾燥やエアコンの除湿運転と同じ方式です。
コンプレッサーの働きで取り込んだ空気を水滴と乾いた空気に分別しているので、デシカント式除湿機と比較して電気代は安いです。
コンプレッサー式除湿機の消費電力は180Wほどの機種が多いです。
電気代に換算すると、1時間あたり5.6円ほどで、1日12時間の使用した場合でおよそ67円です。
デシカント式除湿機の電気代の目安は消費電力300Wの機種を使用した場合で、1時間あたり9.3円程。
1日12時間の使用で112円かかる計算なので、1日あたり45円ほど違ってきます。
特徴②:室温があまり上がらない
ヒーターを使用しないので、室温はあまり変化しません。
メーカーHPなどで除湿機の紹介ページを見ると、
「冷房効果はありません。モーターが熱を発することがあるので、温度はあがります」と注意書きをしています。
温風は出ませんが、デシカント式除湿機を使用した場合と比較すると、部屋の温度は上がりにくいという認識で問題ないかと思います。
特徴③:広い空間に適している
1日あたりに除湿できる量の多い機種があります。
多いもので20〜25Lを一日あたりで除湿することができます。
木造の建物だと20〜25畳ほど、マンションなど鉄筋の建物の場合だと40畳ほどの範囲の除湿ができます。
使用する部屋の気密性や構造によって変わりますがおおよその除湿範囲はこのように言われています。
デメリットとしては
1,振動が大きい
2,本体が大きくて重たい
3,気温で除湿量が変わる
この3点がデメリットと言えます。
【デメリット①:振動が大きい】
本体を稼働させ始めた時など、コンプレッサーが振動します。
運転音が大きいと言われることが多いコンプレッサー式除湿機ですが、振動が大きく、その音が響いてしまうので大きいという意見もあります。
そして、常に振動し続けるのでなく、一時的なことが多いです。
デメリット②:本体が大きくて重たい
コンプレッサーが内蔵されているので、本体は大きく、重量もあります。
広い部屋に対応した機種もありますが、適応畳数が大きくなると本体の重量も増えます。
多くの機種にはキャスターが付いているので、本体を持ち上げるのは大変ですが移動させるのはそこまで大変ではないかもしれません。
デメリット③:気温で除湿量が変わる
コンプレッサー式の除湿機は、気温が15℃あたりから除湿能力が落ち始め、5℃以下になるとほとんど除湿しなくなります。
周囲の空気を取り込み、冷却をして放出するのですが、気温が5℃程度の場合、取り込んだ空気が既に冷えているのであまり効果を発揮できません。
ハイブリット式除湿機の特徴
最後にハイブリット式除湿機について解説します。
ハイブリット式除湿機とは、その名の通りデシカント式除湿機とコンプレッサー式除湿機の特徴を組み合わせたものです。
特徴はこの通りです。
①気温の影響を受けずに除湿できる
②運転によって部屋の温度に影響を与えにくい
デメリットは
①コンプレッサーが内蔵されているので本体が大きく、重たい
②本体価格が高め
メリットもデメリットも、特徴的な部分を取り込んでいます。
ここまでそれぞれの除湿機の特徴とデメリットを解説しました。
もう少し細かく解説していきます。
タンク容量とサイズ
除湿機は湿気と空気を分ける役割の家電なので、空気に含まれていた水分はただの水になります。
その水を貯めるタンクがどの除湿機にも搭載されていて、機種の大小によってタンクの大きさも変わります。
タンクの大きさは4L〜6L程度の機種が多いのですが、10L、20Lのタンクを搭載している業務用のものもあります。
また、本体の中にある排水口にホースを直接繋ぐことで、タンクに水を貯めずに連続排水できる機種もあります。
排水先に気をつける必要がありますが、長時間運転される方にはピッタリの機能です。
部屋の広さに応じた除湿能力
エアコンや加湿器のように、除湿機にも適応畳数があり、鉄筋や木造などの建物の気密性によって除湿能力も変わります。
カタログやメーカーHPの表記としては
・適応畳数
・除湿可能面積の目安
・1日あたりの除湿能力
このような表記があるところを見ながら機種選定をします。
販売されている除湿機の多くは1日あたりの除湿能力4L〜6Lの物が多いです。
この場合の適応畳数は木造の場合6畳〜7畳、鉄筋の場合12畳程度が適応畳数ということになります。
除湿能力が高くなるにつれて適応畳数が増えていくということになります。
洗濯物を乾かす目的であればそこまで高いものでなくて良くなりますし、部屋全体の除湿をしたいのであれば除湿能力が高い機種を選ぶことになります。
使用シーン別で考える
適応畳数を決める?難しい…
と感じたら、除湿機の使用目的を先に決めましょう。
洗濯物を乾かす目的であればそこまで除湿能力の高いものでなくて良くなりますし、部屋全体の除湿をしたいのであれば除湿能力が高い機種を選ぶことになります。
除湿機は本体に取り込んだ空気を水と乾いた空気に分ける家電です。
サーキュレーターや扇風機と併用して、部屋の中の空気を循環させると本体に空気を取り込みやすくなるので、結果的に早く除湿することができます。
操作性と静音性
【操作性】
除湿機はその性質上、複雑な操作をする家電ではありません。
基本的には電源の入り切りと、除湿運転の強弱、必要に応じてタイマーの設定と、主な操作はこのようなものです。
水の溜まったタンクの着脱方法と持ち運び、排水のしやすさ、お手入れのしやすさなどはよく確認することをおすすめします。
また、コンプレッサー式除湿機は本体の重量があるので、部屋の移動をする場合はキャスターがついているかという点も確認するポイントです。
【静音性】
除湿機は運転音のことを気にされる方が多くいらっしゃる家電です。
先ほどもコンプレッサー式除湿機の特徴として、運転音が大きいという点をデメリットとして解説しています。
機種ごとによって運転音の大きさは変わります。
どんな家電であっても動作している以上稼働音はするもので、コンプレッサー式除湿機は特に運転中に振動します。
この点は注意点になるのですが、販売メーカー側は振動する音を動作音として測定していない事があります。
本体の稼働時の音量は、機種単体で見たら、静かだと言われているデシカント式除湿機より、コンプレッサー式除湿機のほうが静かな機種もあります。
次に、それぞれの除湿方式のおすすめ機種をそれぞれ3機種ずつ紹介していきます。
方式別 除湿機おすすめランキング3

では今年おすすめの除湿機をご紹介していきます。まずはコンプレッサー式かたいきましょう
コンプレッサー式除湿機おすすめ
①シャープ CV-S71
②コロナCD-S6324
③三菱MJ-P180WX
この3機種をおすすめします。
それぞれ特徴を解説していきます。
1つ目のシャープCV-S71は、本体の大きさが小さいです。
幅303×奥行203×高さ524 のA4用紙程度の大きさで、6畳から8畳くらいの部屋の除湿や衣類乾燥に適したサイズです。
シャープの製品なので、もちろんプラズマクラスターは搭載されています。
湿気が多い時期になると気になるのがカビや部屋干し臭。
除湿機本来の効果とプラズマクラスターによってどちらにも効果があります。
除湿機でメーカー別のシェアを見ると、現在はシャープが人気となっています。
2つ目コロナCD-S6324は先ほど紹介したシャープのCV-S71と比較すると、本体が少し大きくなります。
水のタンクの大きさがCD-S6324のほうが大きくなるためです。
CD-S6324の特徴は、運転音が静かなことです。
運転音は35dB程度で、この静音性はトップクラスに運転音が小さいです。
図書館の中の騒音値が約40dBなので、かなり静かな機種と言えます。
適応畳数は6畳から8畳で、価格帯も2万円程度で販売されているので、手に取りやすい機種です。
3つ目の三菱MJ-P180WXは、広い部屋の除湿に向いている機種です。
木造などの場合は23畳、鉄筋など気密性が高い部屋の場合は45畳まで対応できます。
運転音の大きさも弱モードで運転時に38dB、強モードの運転時でも46dBと、こちらも静かな運転音の機種です。
本体が大きい機種なので重量も15キロと移動させる場合は重量がありますが、キャスターが付いているので、移動のときには活用するようにしましょう。
デシカント式除湿機おすすめ
次にデシカント式のおすすめ機種を3機種紹介します。
①シャープ CV-S60
②パナソニック F-YZX60B
③日立 HJS-DR601
この3機種をおすすめします。
まず1つ目のCV-S60は、本体が小型であることです。
本体寸法は幅300×奥行300×高さ323で、先ほど紹介したCV-S71と比較すると高さが低くなっています。
部屋干しした衣類の下に配置して、衣類の下から送風して乾かすことができます。
プラズマクラスターも搭載しているので、カビやニオイ対策もできます。
2つ目のパナソニック F-YZX60Bは、デシカント式の中では電気代が安いという特徴があります。
消費電力285Wは、デシカント式除湿機の中では省エネ性が高く、1時間あたり8.8円で運転します。
パナソニックの製品なので、こちらにもナノイーが搭載されています。
また、デシカント式除湿機の中では除湿範囲が広めで、木造の場合7畳、鉄筋などの場合は14畳まで除湿することができます。
3つ目は日立 HJS-DR601です。
本体の重さが5.9kgと比較的軽量、本体の大きさは幅301mm奥行き204mm高さ502mmとコンパクトで、持ち手もついているので、持ち運びも比較的楽にできます。
価格も安く、価格コムでは20000円以下の値段帯で販売されています。(2025年5月時点)
洗濯物の乾燥だけでなく、クローゼットのある部屋まで移動させて使いたい…といった、様々な場所で使用される方におすすめです。
ハイブリッド式除湿機おすすめ
①シャープ CV-SH150
②パナソニック F-YHX90B
③パナソニック F-YHX200B
この3機種をおすすめします。
1つ目のシャープCV-SH150はプラズマクラスターを搭載しています。
先ほど紹介した2機種はプラズマクラスター7000という規格が搭載されています。
ハイブリット式のCV-SH150はプラズマクラスター25000という規格で、プラズマクラスター7000より多くのプラズマクラスターを空気中に放出します。
適応畳数も木造の場合で15畳と広く、衣類乾燥も約57分で乾燥でき、この乾燥時間は業界最速級の速さです。
2つ目はパナソニック F-YHX90Bです。
この機種にはナノイーXが搭載されています。
コンプレッサー式除湿機のおすすめで紹介した機種のF-YZX60Bとは異なり、効果が高いものとされていて、送風運転によるカビやニオイ対策に高い効果があります。
パナソニックの除湿機は全体的に消費電力が低いのが特徴で、強モードで運転しても170Wで、一時間あたりの電気代は約5.3円とかなり省エネ性が高くなっています。
3つ目はパナソニック F-YHX200Bです。
F-YHX90Bのとの違いは適応畳数です。
F-YHX90Bは木造の場合で8畳、F-YHX200Bは木造の場合で19畳まで対応可能となっています。
湿度センサー、温度センサーも搭載しているので、運転も自動でコントロールしてくれます。
165cmの広範囲に送風できる強力な除湿能力を通年使用できます。
それぞれの除湿方式のおすすめ機種を紹介しました。
最後に、除湿機の電気代を抑える方法を紹介します。
除湿機の電気代を抑える方法
①サーキュレーター、扇風機と併用する
②メンテナンスの方法と頻度
この2点を解説します。
サーキュレーター、扇風機と併用する
除湿機は本体に取り込んだ空気を除湿します。
サーキュレーターや扇風機と併用することで効率が上がります。
この辺はエアコンでも同じことが言えますね。
効率が上がれば運転時間を短くすることができるので、結果として電気代を抑えることができます。
サーキュレーターや扇風機自体の電気代は非常に安いので、併用することによる追加コストは大きくありません。
トータルで考えると電気代は安くなります。
メンテナンスの方法と頻度
吸気口にはフィルターが取り付けられています。
このフィルターはホコリが溜まりやすいので定期的に掃除しましょう。
空気を取り込む効率が下がってしまうので、長時間運転する必要が出てしまいます。
使用する頻度によって変わりますが、2週間に一度、または排水タンクに溜まった水を捨てる時など、頻度よくメンテナンスをするようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
除湿機は機種選定に少しコツが要ります。
その家電を使って何がしたいのか?
この基準で選ぶようにしましょう。
今回の動画が皆さんの家電選びの決め手になったら嬉しく思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。